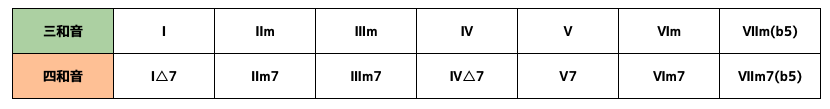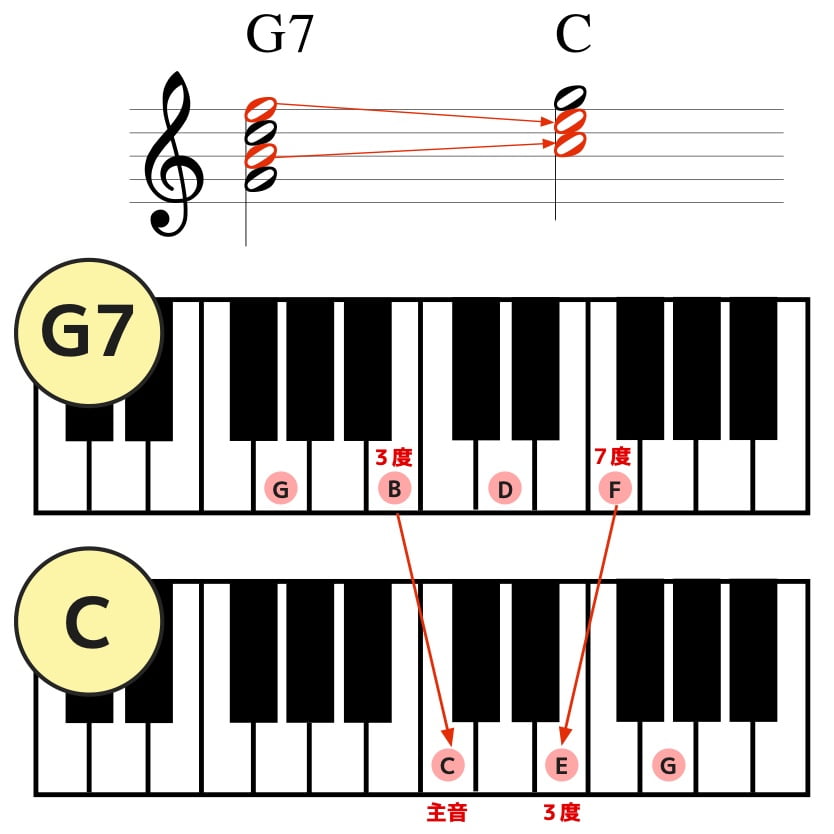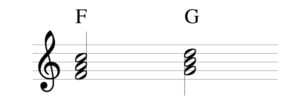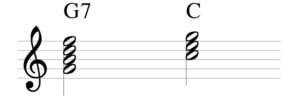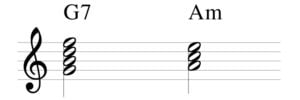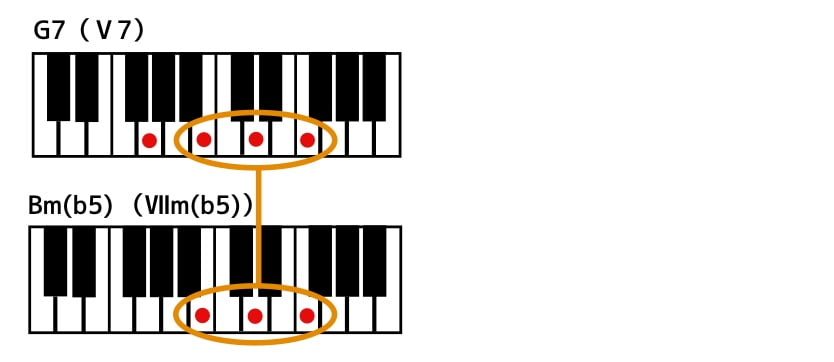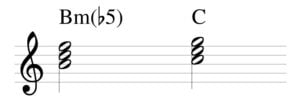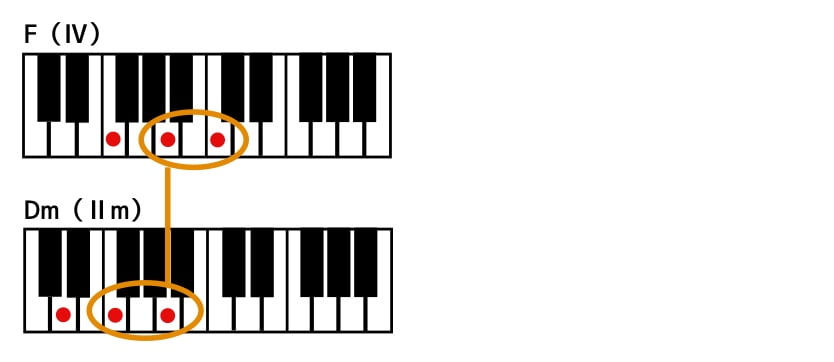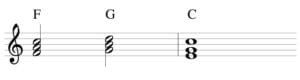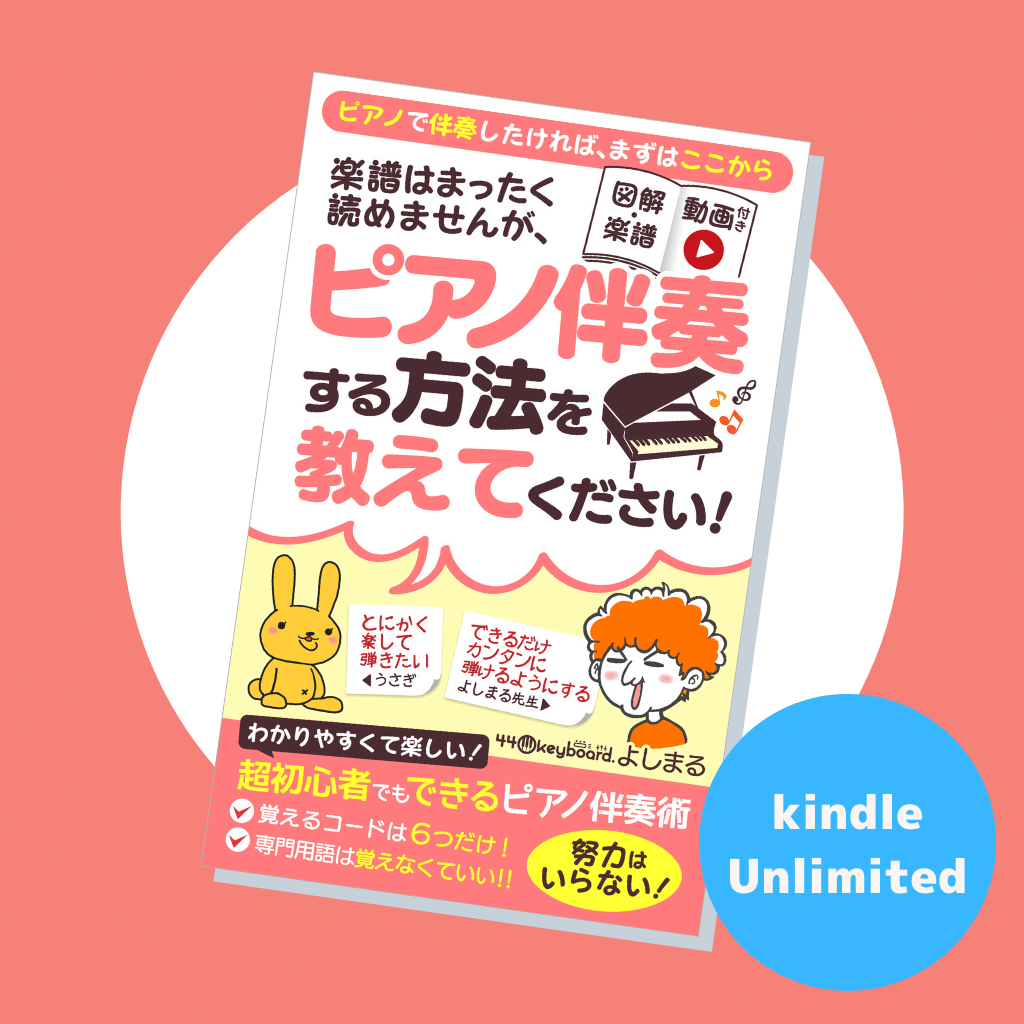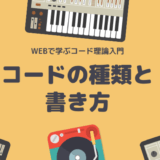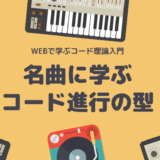「コード理論」初心者入門コーナー
ポップスで使える初心者向けのコード理論を解説していくシリーズです。
さて、前回までのお話を踏まえて、改めてダイアトニックコードをみてみましょう。
ディグリーネームで表にまとめるとこうなります。
今回はダイアトニックコードひとつひとつが持っている「役割」について解説していきます。
コードの役割といわれてもピンとこないかもしれませんが、和音が持つ響きは他の響きと関係しあっているんです。
実際に音を聴きながらみていきましょう!
 うさぼんぬ
うさぼんぬ
主要三和音とは?
ダイアトニックコードにおいて主要とされる3つの和音があります。
それがこちら。
それぞれのコードには和音としての役割があります。
トニック(T)
トニック(Tonic)はキーの中心となるコードです。
キーの中で最も安定・安心感があり、落ち着いた響きを持っています。
あらゆる楽曲がトニックコードで終わるのは、落ち着いた響きゆえに終わった感が得られるからです。
最近は、終わった感じがしないトニック以外のコードで終わる曲も増えています。
ドミナント(D)
ドミナント(Dominant)は、ダイアトニックの中で最も不安定な響きを持ちます。
不安定なので落ち着きたい。すなわち、トニックに進行したいという特性を持っています。
ドミナントからトニックへの進行のことを「ドミナントモーション(別名:強進行)」と呼ばれます。
サブドミナント(SD)
サブドミナント(Sub Dominant)は、汎用性が高いコードでいろんなコードに進行しやすい特性があります。
コード進行のバリエーションをつくるときに活躍してくれるコードです。
 うさぼんぬ
うさぼんぬ
 まえばよしあき
まえばよしあき
代理和音
ダイアトニックの主要三和音がわかったところで、他のコードはどうなのかを見てみましょう。
実は他のコードも、トニック・ドミナント・サブドミナントのいずれかの役割があります。
代理の和音=代わりに使うことができる、ということですね!
コードを入れ替えてみると、同じメロディーでも違った雰囲気を得ることができます。
代理和音は、コード進行のバリエーションを増やすためのとても大切な考え方です。
トニックの代理和音
代理和音の考え方として、共通音を持っていることがあります。
トニックの代理和音はこのふたつ。
- Ⅲm(Ⅲm7)
- Ⅵm(Ⅵm7)
共通の音がそれぞれ2つ以上入っています。
 まえば
まえば
さきほどのドミナントモーションを置き換えてみるとこんな響きになります。
 うさぼんぬ
うさぼんぬ
 まえば
まえば
ドミナントの代理和音
ドミナントの代理和音はひとつだけ。
- VIIm(b5)(VIIm7(b5))
これも構成音を見てみるとわかりますが「トライトーン」が含まれてます。
こちらもトニックへ進行するコードとしてよく使われています。
 うさぼんぬ
うさぼんぬ
 まえばよしあき
まえばよしあき
サブドミナントの代理和音
こちらもサブドミナントの特性を強くもつ音を2つ以上含むコードになります。
- IIm(IIm7)
サブドミナントを決定づけるのは4番目の音。(この場合ファ)
この音を含むコードなので、響きが似ていますね。
実際に置き換えた響きを聞いてみましょう。
この記事のまとめ
いかがでしたか?
ダイアトニックコード7つが持つ役割について解説してきました。
各コードの役割が、「コードの流れすなわちコード進行」をつくりだしあらゆる楽曲に使われているというわけです。
次回は実際にスピッツのチェリーを題材にして、曲を見ていきたいと思います。
 うさぼんぬ
うさぼんぬ
- ダイアトニックコードひとつひとつには役割がある。
- ダイアトニックの、主要三和音の役割は「トニック(T)・ドミナント(D)・サブドミナント(SD)」の3つに分類できる。
- トニック:曲の中心になるコードで最も安心感がある。
- ドミナント:最も不安定な響きでトニックに行きたくなる。その理由はトライトーンという音程にある。
- サブドミナント:汎用性が高く、コードのバリエーションを作るときに活躍。
- T・D・SDの役割は他のダイアトニックコードにも割り当てることができる。
- これらの組み合わせで楽曲のコード進行は作られている!
【ベストセラー】初の電子書籍出版!
超初心者が初心者になるための「ピアノ伴奏」決定版!楽譜・図解・動画付きで楽譜が読めない人でも安心♪
【読者限定特典】コード伴奏をマスターするエクササイズ付き!
超実践的なメソッド配信!
登録者限定ピアノレッスン、セミナー資料プレゼント、キャンペーン情報など。ブログには書かないおトクな方法をお届け。
バンド・セッション・弾き語り・ソロピアノまで、幅広く使える「オシャレ」で「超実践的」な独自メソッドを知るチャンス!